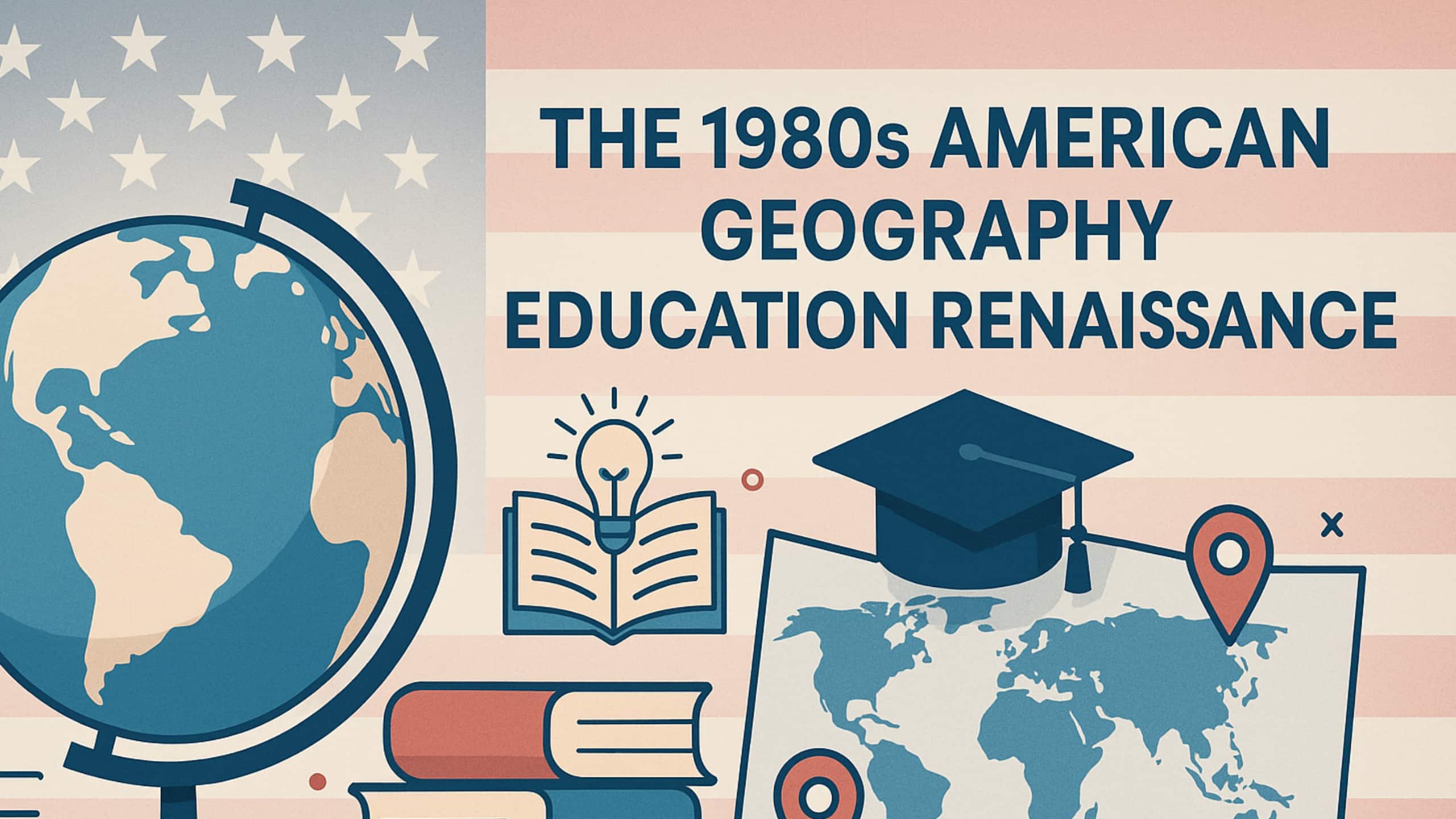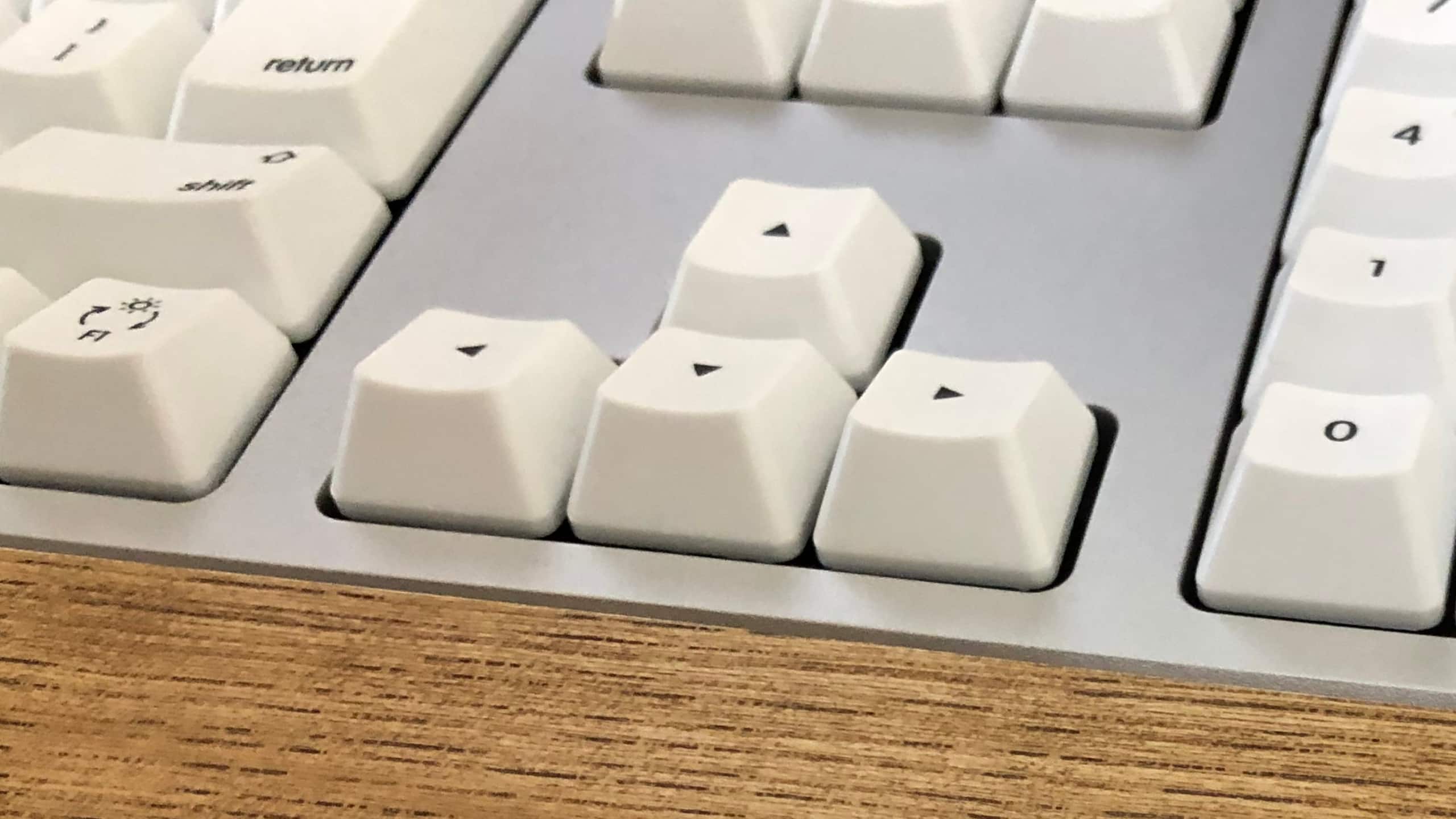先日、ある学校が主催したオンライン講座に参加しました。発表後の質疑の時、カザフスタン出身という方が「日本の方と話していると、カザフスタンがどこにあるのか知らない人がいてびっくりした。受験勉強して大学を出た方もいるのに、地理的な知識があまり身についていない方がいるのは不思議です・・・」というようなことを話していたのが印象に残っています。統計的に正しいことははっきりしませんが、このカザフスタン出身の方とお会いしている方々の場合はそういう実態なのでしょう。高校生になると「地理」を学ばない方もいる期間も長かったですし、マスメディアによる報道の少なさも影響しているのかもしれません。
そんなこともあったので、今回は「地理教育」の話題を取り上げることにします。大半はアメリカの話ですが・・・
はじめに 〜なぜ今、地理教育が注目されるのか〜
グローバル化が急速に進む現代社会において、空間認識能力や地理的リテラシーの重要性が高まっています。日本でも2022年度から高等学校で「地理総合」が必修科目となり、地理教育の在り方が大きく注目されています。
「地理って何を教えるの?」という問いは、簡単なようで非常に複雑です。戦後日本の社会科教育はアメリカ合衆国のSocial Studiesを模範として成立しましたが、そのアメリカでも1980年代に「地理教育復興運動(Geography Education Renaissance)」が起こり、地理教育の意義や手法が大きく見直されました。
この運動は、グローバル化が進む現代社会において、空間認識能力や地理的リテラシーの重要性が高まっていることと密接に関連しています。アメリカの経験から、現在の日本の地理教育改革に多くの示唆を得ることができるでしょう。
アメリカ地理教育復興運動の背景と原動力
危機意識から生まれた改革の必要性
この運動の原動力となったのは、「危機に立つ国家-教育改革報告書(A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, 1983)」や「外国語と世界学習推進委員会(大統領委員会)報告(President’s Commission on Foreign Language and International Studies, 1979)」など、アメリカの児童・生徒の学力水準低下や地理的知識の不足を国の存亡にかかわる重大課題と位置付ける報告書の存在でした。
これらの報告書は、単に教育の質の低下を指摘するだけでなく、国際競争力の観点から地理的知識の重要性を強調しました。特に冷戦時代という国際情勢の中で、アメリカ国民の世界に対する理解不足が国家安全保障上の問題として認識されたのです。
深刻な地理的知識不足の実態
実際、1988年から1989年にかけて実施された10カ国のギャラップ調査では、アメリカ人の地理的知識は下位3分の1に位置し、特に18歳から24歳の若年層は最下位という結果が出ました。この結果は、アメリカ社会に大きな衝撃を与え、地理教育改革の必要性を広く認識させることとなりました。
地理教育復興運動の組織化と展開(1980年代前半)
委員会とガイドラインの成立
**地理学および国際知識委員会(Committee on Geography and International Knowledge)**が1982年に新設され、地理教育改革推進の中核を担いました。この委員会は、地理教育の現状分析と改革方針の策定を行い、後の具体的な取り組みの基盤を作りました。
1984年には、全米地理教育協議会(National Council for Geographic Education: NCGE)とアメリカ地理学会(Association of American Geographers: AAG)の合同委員会により「初等および中等学校用地理教育ガイドライン(Guidelines for Geographic Education: Elementary and Secondary Schools)」が策定されました。このガイドラインは地理教育復興運動の「バイブル」とされ、地理教育カリキュラム整備の重要指標として広く導入されました。
画期的な「地理学の5大テーマ」の提唱
ガイドラインで提唱された「地理学の5大テーマ(Five Themes of Geography)」または「地理学の5つの基本テーマ(Five Fundamental Themes of Geography)」は、地理教育の内容を明確化する画期的な枠組みでした。
- 位置(Location):地表面における絶対的・相対的位置
- 場所(Place):自然的・人文的特徴による場所の特性
- 場所における相互関係(Human-Environment Interaction: Relationships within Places):人間と環境の相互依存関係
- 移動(Movement):地表面における人間、物資、情報の移動
- 地域(Regions):地域の形成過程と変化
これにより、「何を教えるか」という目的・内容の整理が飛躍的に明確化され、従来の曖昧さを払拭しました。この5大テーマは、後に日本の学習指導要領における「地理的な見方・考え方」にも影響を与えることとなります。
全国規模のネットワーク構築と人材育成(1980年代後半)
地理教育連合ネットワークの展開
**地理教育連合ネットワーク(Geography Education Alliances Network)**として、全米地理学協会(National Geographic Society: NGS)は、各州レベルで地理教育の向上を目指すネットワークを全国的に構築しました。47州に教育者や地理学者、政策担当者による連合が設立・連携され、地方から国家レベルの改革を推進しました。
このネットワークは、単なる情報共有にとどまらず、各地域の実情に応じた教材開発や指導法の改善を促進する実践的な役割を果たしました。
大規模な教師研修プログラム
NGSの主導で4週間の夏期合宿をはじめとした教師向けトレーニングが提供され、1988年には恒久的な教育基金も創設されました。1992年までに15万人以上の教員が研修を受け、各州教育現場に知見が還元されました。
この研修プログラムの特徴は、参加教師が学校に戻って同僚と知識を共有することが前提とされていた点です。これにより、限られた予算で最大限の効果を上げる「連鎖的な研修効果」を実現しました。
全国規模イベントと教材開発(1980年代後半~1990年代)
ナショナルジオグラフィック・ビーの創設
1989年、全米地理学協会が「ナショナルジオグラフィック・ビー(National Geographic Bee)」を創設しました。4年生~8年生の児童・生徒を対象に地理的知識を競う大会で、初回は1989年5月19日にワシントンD.C.で開催されました。
司会は人気クイズ番組『ジェパディ!(Jeopardy!)』のアレックス・トレベック氏が担当しました。『ジェパディ!』はアメリカを代表する知識クイズ番組で、出題方式や分かりやすい進行によって高い視聴率と長い歴史を持つ番組です。この著名な司会者の起用により、ナショナルジオグラフィック・ビーは一般社会の注目を集めることに成功しました。
現在、ナショナルジオグラフィック・ビーは毎年数百万人規模の児童・生徒が挑戦する全国イベントとして定着しています。
国際的な教材開発の推進
1990年代には国際的な地理教材開発も積極的に行われ、特に「米ロ地理教材共同開発プロジェクト(U.S.-Russia Joint Geography Education Project)」として、アメリカとロシアの共同プロジェクトによる教材の開発・交流が推進されました。
これは、冷戦終結後の新しい国際関係の中で、相互理解を深めるための地理教育の役割を示す象徴的な取り組みでした。
教育基準の確立とその発展(1990年代)
National Geography Standardsの完成
1994年、全米地理学協会を中心に地理教育の国家標準(ナショナルスタンダード)として「Geography for Life: National Geography Standards」が発表されました。K-12(小学校~高等学校)全学年を対象とし、18のスタンダードが6つの「基本要素(Essential Elements)」に整理されています。この6つの基本要素は以下の通りです:
このスタンダードは、「Geography for Life: National Geography Standards」として書籍化され、2012年には内容を21世紀型スキルや新しい地理的課題に対応した改訂版(Second Edition)も出版されています。
- 空間的視点での世界理解
- 場所と地域
- 物理的システム
- 人間システム
- 環境と社会
- 地理学の応用
21世紀への対応
このスタンダードは、「Geography for Life: National Geography Standards」として書籍化され、2012年には内容を21世紀型スキルや新しい地理的課題に対応した**改訂版(Second Edition)**も出版されています。改訂版では、GIS(地理情報システム)やデジタル技術の活用、持続可能な開発目標(SDGs)への対応など、現代的な課題が盛り込まれました。
日本の学習指導要領における「地理的な見方・考え方」との関連
2017年改訂学習指導要領での位置づけ
2017年の日本の学習指導要領改訂では、アメリカの地理教育復興運動と類似した概念として「地理的な見方・考え方」が明確に位置づけられました。この概念は、三次元空間における物体の位置・形状・方向・大きさ・位置関係などを素早く正確に認識する能力である空間認識能力と深く関連しています。
アメリカの「5大テーマ」との共通点
アメリカの地理学5大テーマと日本の「地理的な見方・考え方」には、以下のような共通点があります:
- 空間認識の重視:位置関係や空間的な配置を重視する視点
- システム思考:自然と人間の相互作用を体系的に捉える視点
- スケールの概念:地域から世界まで、様々なスケールでの思考
- 動的な視点:変化や移動を捉える動的な見方
これらの共通点は、地理教育における普遍的な価値を示すものとして注目されます。
コンピテンシー論との関連
21世紀型能力とコンピテンシー・ベース教育
近年の教育界では、OECD「Future of Education and Skills 2030 プロジェクト」において、現代の子どもが成長して世界を切り拓いていくためには、どのような知識やスキル、態度および価値が必要かを検討し、進化し続ける学習の枠組みとして「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)」が作られました。このコンピテンシー論の広がりは、地理教育にも大きな影響を与えています。
地理的コンピテンシーの構成要素
地理的コンピテンシーは以下の要素から構成されます:
- 認知的スキル:3次元空間において自己と空間の相対的位置関係を把握すること
- メタ認知スキル:地理的思考プロセスを意識的に活用する能力
- 社会的・情緒的スキル:多様な文化や環境に対する理解と共感
- 実践的スキル:地理的知識を実際の問題解決に活用する能力
これらの要素は、アメリカの地理教育復興運動で重視された能力と多くの共通点を持っています。
アメリカ地理教育復興運動の意義と影響
社会全体の意識改革
この1980年代の運動は、単なるカリキュラム改革に留まらず、アメリカ社会全体の地理リテラシー向上への意識改革となりました。学校教育にとどまらず、市民一人ひとりが地理的視点を持って世界を理解し、グローバル時代を生きるための基礎力を重視する社会的運動として発展したのです。
国際的な影響力
こうした動向は、その後の国際協働や他国の教育改革にも影響を与えるまでになりました。特に、地理教育の目標や内容を明確化する手法は、多くの国で参考にされています。
日本の地理教育改革への示唆
アメリカの経験から学ぶ改革のポイント
アメリカの地理教育復興運動や今日のコンピテンシー論の現状を考慮すると、いくつかのポイントを学べるような気がします。
- 明確な教育目標の設定:「地理的な見方・考え方」をより具体的に定義し、教育現場で活用しやすい形で提示
- 関係組織の連携:教育現場、学会、政策立案者の協働体制の構築
- 継続的な教師研修:新しい教育観に基づく指導法の普及と定着
- 評価方法の改善:コンピテンシー評価に対応した新しい評価手法の開発
- 社会全体の地理的リテラシー向上:学校教育を超えた生涯学習の推進
まとめ 〜持続可能な改革に向けて〜
アメリカの地理教育復興運動が成功した要因は、組織的な取り組み、明確な目標設定、継続的な研修、そして社会全体を巻き込んだ運動として展開されたことにあります。
このように、アメリカの地理教育復興運動とその成果物は、地理教育の意義や共通理解をわかりやすく可視化し、改めて地理という学問の重要性を現代社会に位置づけ直す画期的な役割を果たしたと言えます。
日本においても、「地理って何を教えるの?」という疑問に対する答えを見つけるためには、アメリカの経験とコンピテンシー論の知見を統合し、日本の教育文脈に適した地理教育の枠組みを構築することが必要になってくると思います。そして、それは単に知識の伝達にとどまらず、現代社会を生きる市民として必要な地理的思考力と実践力を育成する教育へと発展させていくことが求められているるということになるのだと考えています。
こうしたことは「地理」だけに言える話ではないわけですが、あまり広げないようにしておきます。余裕があれば、その後の動きについてもそのうち紹介してみたいと考えています。