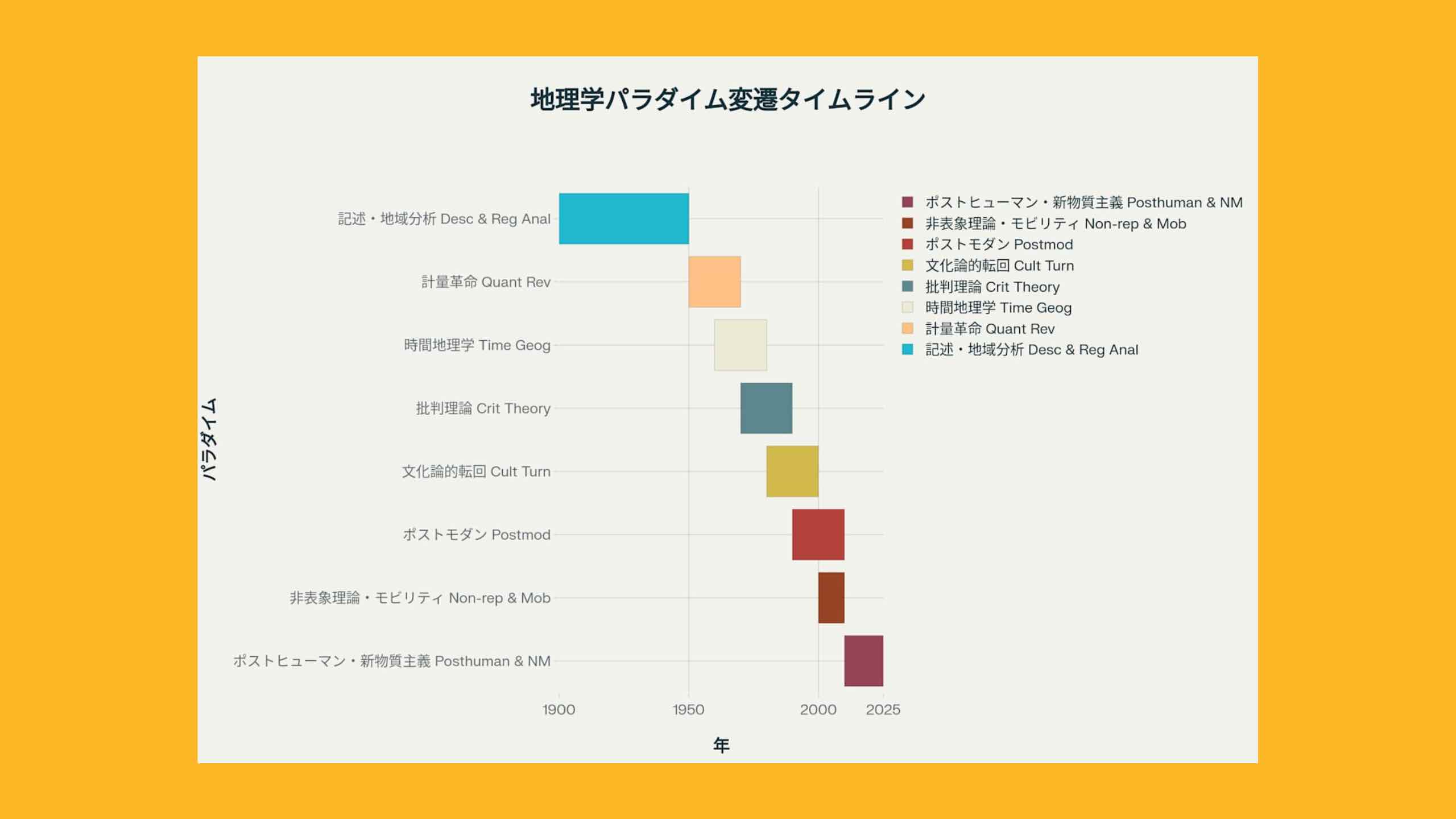旅行で出会った不思議な建物
去年の夏、旅行でニューヨークに行きました。チェルシーマーケットを楽しんだ後、ハイラインを歩きました。ハイラインは、廃線となった高架線路を緑豊かな遊歩道として再生した都市型公園で、多くの観光客で賑わっていました。
このハイラインの北端にあるハドソンヤードに到着すると、そこには独特の形をした巨大な建築物「ベッセル」がありました。当時は閉鎖中で登ることはできませんでしたが、この不思議な建物を見ることができたのが印象に残っています。
実は、このベッセルを私が知ったのは、地理学者デヴィッド・ハーヴェイがハドソンヤード地区で解説している動画を見たからでした。その動画の内容が、再び都市での生活について深く考えるきっかけとなりました。
都市空間と資本の関係を読み解く
動画では、ハーヴェイがベッセルを含むハドソンヤード周辺を歩きながら、都市空間と資本の関係について語っています。
“David Harvey and the City” ― Antipode Foundation(2020年)
都市の「パリンプセスト」:歴史の重なり合い
ハーヴェイは「パリンプセスト(palimpsest)」という地質学的メタファーを用いて、都市の成り立ちを説明しています。都市とは、異なる時代の開発が層状に重なった地形だというのです。
かつて貨物輸送用高架鉄道だったハイライン跡地が、1970~80年代に廃れ、再開発の権利を巡る争いを経て現在の観光名所になった歴史がその典型例です。ベッセルやハドソンヤードも、こうした「権利闘争」の帰結としての都市空間の断面として捉えることができます。
資本主義の「空間的回避」のメカニズム
資本主義経済では、資本は存続のために常に正の成長率での拡大を迫られます。都市が「完成」すると次の拡張先が必要となり、郊外開発や高層ビル建設へと向かう「空間的回避(spatial fix)」を生むのです。
ベッセルやハドソンヤードは、こうした過剰流動性(使い道を失った資本が不動産に向かう現象)の典型例であり、公共サービス削減下での「モニュメント建設」が象徴する矛盾を浮き彫りにしています。
住居の商品化:使用価値から交換価値への変化
ハーヴェイは、かつて「住居=使用価値」であったものが、次第に「交換価値=投資対象」へ変質した歴史的経緯を指摘します。1960~70年代のブロックバスティング(人種を利用した不動産投機)の経験を通じ、「誰が人種的分断から利益を得るのか?」を問い続けました。
1990年代以降、住宅は「修繕→転売」の投機対象となり、現在では超富裕層の資産保管庫として建設され、低所得層の「住まい喪失」を助長する構造が顕在化しています。
都市の政治的意味:市民性と帰属意識の重要性
ハーヴェイは、都市を単なる物理的構造物ではなく「市民性(citizenship)と帰属意識を生み出す政治的概念」として捉えることの重要性を説いています。ベッセルのような新モニュメントは、「超富裕層の愚行の記念碑」として批判的に読み解くべきであり、市民としての連帯―公共の場の再獲得―が求められます。
現代に続く構造的問題
ハーヴェイがベッセルを「超富裕層の愚行の記念碑」と呼ぶのは、1960-70年代にアメリカで横行したブロックバスティングと同じ構造を見ているからです。
その構造とは以下のようなものです:
- 資本の利益のための空間操作
- 公共性の犠牲による私的利益の追求
- 社会的分断の深化
「誰が利益を得るのか?」という問いは、現代の都市問題を理解する上で依然として重要です。表面的な「発展」や「改善」の背後にある利益構造を見抜くことで、真の社会的正義を実現する道筋が見えてくるのです。
希望としての市民的空間の再構築
たとえ大規模再開発地でも、市民が「都市の一部を再公共化する」運動を起こすことで、再開発地における空間の所有・利用ルールを覆すことが可能だとハーヴェイは語っています。
具体的には、公共広場や公園のデザインに市民参加を取り入れる、地元住民や芸術文化グループに優先利用権を与える、空間利用ルールを「開かれた共用地」として設定するといった取り組みが考えられます。
おわりに
ニューヨーク旅行で偶然出会ったベッセルという建物が、都市と資本、そして市民の関係について深く考えるきっかけとなりました。私たちが住む街も、同じような課題を抱えているかもしれません。
「誰のための街づくりなのか?」という問いを持ち続けることで、より良い都市の未来を創造できるのではないでしょうか。ハーヴェイの提起する市民的空間の再構築という視点は、現代を生きる私たちにとって重要な指針となるように思います。